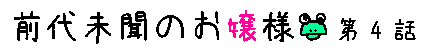 千里たつき (結局帰ってこなかったわ。何の音沙汰もないし・・・) 棚を埋め尽くす沢山のテディベアに、薄桃色の斜陽カーテン、ナチュラルブラウンの木製チェスト。好きなものばかりを集めた自分の部屋にいながら、ベッドに腰掛けた秋保枝理紗はため息をついた。窓の外は、深夜に相応しい暗さ。空には数え切れないほどの星が瞬いている。 (私がもっと早くに駆けつけていれば、こんなことにはならなかったかも知れないのに・・・) 何度もそう考えては、その度にぐっと唇を噛んだ。 昼休みに彼女は職員室前で別れたあと、先に音楽室へ行って唯加を待っていたのだが、授業開始のチャイムが鳴る二分前になっても来なかったので、心配になって探しに出たのだった。 (唯加・・・大丈夫かしら。気分が悪くなっていないかしら・・・) 昼間、クラスメイトの前では皆を励ましてさえいたものの、こうしてじっと考え込んでいると、不安が募るばかりだった。 「―――じっとしてはいられないわ」 枝理紗は意を決して呟くと、二つに分けてゆるい三つ編みにしていた髪を解いた。抱きかかえるようにして持っていた大きなテディベアを、ベッドの隅に置く。 「私も、行きましょう」 彼女は言いながら立ち上がって、寝巻き代わりのワンピースの上から、白いカーディガンを羽織った。 ―――待っていてね、唯加。きっと見つけるから。 そして、部屋の外へと飛び出した。 夢を見た。高校に入ってからずっと親しくしていた友人が、忽然と姿を消した自分に呼びかけている夢。 (やっぱり、心配してるわよね・・・) 目覚めた唯加は上半身を起こし、小さくため息を吐いた。 天蓋付きベッドのカーテンを開けると、部屋にある南東に面した窓から暖かい朝の陽射しが差し込んでいた。自然と顔もほころぶ。 ベッドから降た唯加は、裾はフリル、衿はレース、袖はパフスリーブになっている薄緑色のワンピースを姿見で眺め、 「こういうのはあの子のほうが似合うんじゃない?」 そんな独り言をこぼした。 そのとき、彼女のお腹がおおよそお嬢様らしくはないほど派手に鳴った。そういえば体調を崩していて、昨日の昼から何も食べていなかったのだ。 (何か貰いに行かなきゃ) 顔を洗ったあと優美な装飾の入ったドレッサーに向かい、軽く髪を梳いてから、クローゼットの中にあった丈の長いニットを羽織った。 裸足だったが、空腹感に耐えられない唯加はそのまま部屋から飛び出した。けれどすぐ夜通し見張っていたらしいルーメンに止められてしまい、仕方なくシルヴィアに食事を届けてもらうことになった。そして彼女が唯加の部屋に来たのは、それから十数分後のことだった。 「遅くなって、本当にすみませんでした。今朝は城じゅうごった返していまして・・・」 唯加はそう言うシルヴィアを、この世界で唯一の女性の知り合いを、喜んで迎える。 「いえ、いいんです。でもごった返してるって、何かあったの?」 「ええ、少し・・・。後ほど臨時の会議がありますので、お嬢様もお連れします。そのとき詳しくお伝えしますね」 「そう・・・・・・」 微笑を浮かべる疲れた顔が、何だか引っかかる。 (臨時の会議ねぇ・・・) 少しどころではない事態になっていそうだな、と思いながらも、とりあえず今は食事を楽しむことにした。焼きたてのミルクトーストとハムエッグは、十代の女の子に相応しい量だった。 「―――ミルネーシュ・・・南東のはずれか。先代のお嬢様が特別に警戒するよう命じられた観光地だな」 「なるほど、地理的にあの若い領主が治める地方に突き出るようになっていますね。大方、以前から狙っていたのでしょう」 「すると、どこからか我らがお嬢様の席が空白のままと知られたのか・・・・・・」 「しかし隙を突くのなら、もっと護りの薄い街を攻めるのではないか。さらば我々もこれほど早くに勘付けまい」 「待て、まさか新たなお嬢様の資格をお持ちの方をお迎えしたことまでは知られていないだろうな!? 新たなお嬢様が好奇心に駆られ出て行くか、我々が出て城が手薄になるか、そのどちらかを予想して、狙いがあの方なのだとすれば」 「あまりに若い領主だからと甘く見ていましたね・・・」 「くそっ、一体どこまで掴んでるんだ、アキフォーナ家は!」 あのバルコニーのある部屋と同じくらい大きく重そうな扉を前にして、シルヴィアを見た。 「ここが会議室? 本当に入っていいのよね」 「もちろんですわ。・・・お待ちください、少し失礼します」 シルヴィアが唯加の代わりに扉を叩き、中の返事もろくに待たずえいとばかりに取っ手を引く。 「どうした、シルヴィア」 昨夜唯加にバルコニーからの星空を見せてくれた青年、ティグリスが顔を上げた。 「お嬢様をお連れしました」 彼女が扉を更に大きく開いたので、唯加はお礼を言ってから先に中へ入った。集まっている人々はティグリスとラーディンを除く全員が見知らぬ男性で、中央の大きな机の上に広げた地図やら羊皮紙やらを覗き込むようにしていたが、唯加を見ると次々に名乗ってくれた。最後に唯加が、 「阿隅唯加です、よろしくお願いします。それと―――何かあったんですか?」 そう真剣な―――クラスメイトたち曰く頼もしい―――眼差しで問うと、彼らの間から感嘆の息が漏れた。 (側近の者たちによると、あまりに突然の話で我らを受け入れてくださるかわからないという話だったが・・・) なぜこんな、一昨日まで知らなかった世界のことを気にかけるのだろう。 それは唯加自身にもわからなかった。やはり持って生まれた性格で、単にお人好しなのだろう。あまり何でも引き受けるのはやめようと決めたばかりだというのに、いざこんな風に困惑している人たちを見ると話だけでも聞きたくなってしまう。 「あ、訊いといて何なんですが私、まだこの家の当主さんになるつもりはないんです。すみません」 とりあえずそう言っておいた。話を聞くと何かと引き受けてしまうだろうが、“お嬢様”と呼ばれるアスポロナ家当主にだけはなるつもりがないのではっきり言っておくべきかと思ったのだ。 「はい、承知しております」 彼らはそう頷きながらも、唯加の首のペンダントを残念そうに見つめたので、こちらも胸が痛くなった。 「アスポロナ地方の南東のはずれにある街ミルネーシュが、隣接する地方を治めるアキフォーナ家から攻撃を受けたのです。今朝早く・・・夜明け前でした」 ロマンスグレーの髪をきちんと整えた、五、六十代と思しき男性が地図を指し示しながら説明を始める。先ほどヴェーリンギアと名乗っていたが、彼がこの地方全体を管理する領主の代行者らしい。 「攻撃?」 「はい、以前から侵略を目論んでいたのかも知れません」 「以前からって・・・よくあるんですか、こんなこと」 ヴェーリンギアは静かに頷いた。 「そうか、まだご存知なかったのですね。パニティア国の十二の貴族には、それぞれほぼ同等の権力と土地が与えられています。しかし貴族たちの中には、それだけ―――他と同じだけでは満足できない者たちも大勢いるのです」 「それで、他の土地を奪おうとして攻撃してくるんですか?」 「その通りです」 それを聞いて、唯加は急に眉根を寄せた。 「もしかして・・・・・・私が領主になるのを渋ってたから領主不在の状態が長引いて、それが知られて―――」 「違います。そう仰るのなら、我々が貴女をお迎えするのが遅れたためです」 鋭い声でティグリスに遮られたが、唯加は構わず言う。 「それでも私が昨日のうちに、はっきり答えてれば良かったんじゃありませんか?」 「何言ってんだ。たかが異世界の女の言動一つ、一日やそこらで影響しねーよ」 ティグリスの後ろから聞こえた乱暴な声は、もちろんラーディンのものだった。あんたの言い方はいちいちムカつくのよ、とひと睨みしてから、唯加はロマンスグレーの領主代行者を呼ぶ。 「あの、ヴェーリンギアさん」 「ヴェーギアとお呼びください、ユイカ様」 周囲の男性たちと何やら相談していたヴェーリンギアは、彼女の声にすぐ振り向いてくれた。続きを言おうと口を開いて、唯加は一瞬だけ躊躇う。また後悔することになるとわかっていながら、世話焼きでお人好しな自分に呆れながら、重たい口を動かして言葉を繋ぐ。もう乗りかかった船だとさえ思っていた。 「・・・ヴェーギアさん。・・・・・・何か、私が力になれることは、ありますか」 ヴェーリンギアは髪と同じ色の髭の下で、唯加の後悔を吹き飛ばすがごとく微笑んだ。 「もちろん、我々自慢の観光地をご覧くださるだけで充分でございます」 と。 出掛ける支度と称してシルヴィアや他のメイドたちから着せられた、紅いリボンをあしらったワンピースドレスの裾を摘みつつ、内心唯加は嬉しかった。もちろん自分より枝理紗の方が数倍似合うと思ってはいるが、本音を言うと彼女自身こういう服装は好みなのだ。 上機嫌の唯加に、血の気の多い金髪の青年が近付いてきた。 「おい、餓鬼!」 広い廊下をふてぶてしく歩いてくる前当主の息子の姿を見て、持ち場を守っていた部屋番のルーメンが僅かに後ずさる。 「騒動になってる現地にのこのこ出てくって、お前本物の馬鹿だろ。そんなに怪我してぇのか?」 屋敷の者たちに言わせれば無礼なことに、彼は次期当主候補である唯加を睨みつつ嘲笑した。唯加はその鋭い目を見、勝ち気そうに微笑んでやる。 「大丈夫よ、私“お嬢様”じゃないもの。それにまだ直接的な争いにはなってないってヴェーギアさんも言ってたでしょ」 「分かってねぇなー、それでもお嬢の資格は持ってんだろ。行動にもちょっとは気ィ遣えよ。お嬢っつーのは滅多になぁ―――」 「あのねー、私はあんたのお母様じゃないんだからあんたの知ってる“お嬢様”とは全然違うの。分かる?」 お嬢様のあるべき姿を語ろうとしたラーディンの言葉を、早口で遮った。唯加の言ったことに反応したのか、ルーメンが後ろで息をのむ。 「な・・・・・・ッ、俺は母さんのことなんか言ってねー!」 「あぁそう。とにかく私は、自分でやるべきだって思ったことをやるから! こんなことになったのは私の所為でもあるんだし、今はヴェーギアさんたちに付いてって少しでも力にならないと」 「え、おい、ならないとって・・・・・・」 金髪の青年の脇を抜けて歩き出したとき、ティグリスが角を曲がってくるのが見えた。 「お嬢様、ご用意はお済みになられましたか」 「ええ。すぐに行くんですね?」 「はい。ヴェーリンギア卿がいますので、どうぞあちらへ」 彼が指した先を見やると、普段は締め切られている裏口の白い扉が明け放たれ、六人乗りの馬車一台の前にヴェーリンギアの他何人かの男性たちが立っていた。 唯加はすぐに頷いて歩き出す。 一方ラーディンはティグリスに、彼女には聞こえないよう小声で訴えた。 「なぁティグリス、やっぱコイツには無理だ」 今朝早く、彼と共に慌しくとった朝食時に話したことを思い出し、ティグリスは神妙に頷いた。 「・・・・・・そうか・・・・・・しかし自覚しておられないのなら、それは我々の問題とは・・・言えないな」 「ま、そーだな」 ラーディンは如何にもどうでも良さげに、よそ見しながら頭の後ろで手を組んでいた。 裏口付近に集まっていたアスポロナ家の大人たちを前に、唯加は堂々として見えた。彼らが頭を下げるのを止めて、 「私も馬車に乗らせて頂きますね」 と、ごく普通に言った。 「やはり! ならばお嬢様、正式に我らが当主様となって頂けるのですね!?」 「シェフネン卿、焦りすぎだ」 赤褐色の髪をした男性が声を上げたところを、ヴェーリンギアが窘めた。 「は―――申し訳ございません」 「何度も言うようですが、私はお嬢様―――当主さんになるつもりは全然ありません。ただ色々とお世話になりましたしお話も聞かせて頂きましたから、力になれることはしようと思っています。・・・お人好しとは言わないでくださいね、自分でも分かってますから」 苦笑した後、さっきのようなお辞儀なんてしないで欲しい、と付け加えた。 「実はこの馬車は現地での移動の為に用意したもので、ミルネーシュへはまたティグリスの移動の術を使うのですけれど、大丈夫でしょうか?」 シルヴィアには少し無理を言って、ついて来てもらえることになった。馬車に乗る前に念のため、と訊ねられて、唯加は苦笑する。 「大丈夫、・・・だと思う。あーまた気分悪くなっちゃうかしら」 異世界間を移動した昨日に比べればいくぶん楽かと存じます、とティグリスに言われ、唯加はとりあえず安心した。 なのに、 「案の定っていうか・・・うぅ」 移動の術に呑まれ、しばしの間を置いて離れた町に現れた馬車から降りた唯加の足元は、覚束なかった。 「お嬢様、またご気分が!?」 「あ、いえ、ちょっと頭が痛いだけです。昨日よりは全然辛くありませんから!」 ほとんど飛んで来たティグリスとシルヴィアに、唯加はさも何でもなさそうに笑ってみせた。多少のことなら我慢するのが長年の癖になっている。それなら良かった、と彼らも安堵したようだが、そのとき 「来たぞ!」 数メートル離れたところに立つ騎士―――この町、ミルネーシュに以前から配属されていた兵士―――が声を上げた。 「アキフォーナ家の奴らだ!」 今しがた移動してきたばかりだというのに、屋敷にいた者で戦いの経験もあろう者たちは素早く馬に飛び乗った。唯加は初めもう交戦しに行くのかと思いどきりとしたが、彼らが皆数百メートルほど駆けたところで止まり、騎士が指した方向を舐めるように見ているので、様子見に行っただけだと気付いた。 「お嬢様、私とラーディンも馬でひと走りして参ります」 ティグリスの声が聞こえ、唯加も口を開く。 「ティグリスさん、私も連れて行ってください」 「しかし・・・・・・今朝は申し上げませんでしたが、彼奴らは時期当主となられ得る貴女を狙って仕掛けている可能性もあるのです。現に貴女のいらした世界にも、アキフォーナ家の者が・・・」 「・・・そうなんですか。でも・・・それでも、行って見なきゃ。ヴェーギアさんにもそうするって言ったし、それに―――」 唯加はミルネーシュの町を遠目に眺める。レンガの赤茶色に統一された綺麗な町だった。彼女らが今集まっているのは町はずれの大草原で、花が咲く季節には観光名所の一つにもなると聞いた。 「こんなに素敵な町を攻撃して、あなたたちみたいないい人たちを困らせるのはどんな酷いお嬢様か、見てみたいしね」 普段の頼もしい笑みに、悪戯めいた好奇心を加えたような表情を見て、ティグリスは根負けしたように息を吐く。 「・・・・・・解りました」 そして微笑んだ。つられたように。 またも無理を言って走らせた馬車の中から、アキフォーナ地方の騎馬隊が見えた。先頭に立つ白っぽい馬に跨る少女を見て、唯加は何か思い当たったようだった。 「あれは・・・・・・?」 馬車の小窓の外から、騎乗したティグリスの声が答える。 「最前列中央の葦毛に乗る少女ですか? 彼女がアキフォーナ家の若き当主のようですね」 「当主って・・・例の酷そうなお嬢様なの? この世界の?」 「そうですが」 「だって・・・そんな、嘘・・・」 だって、あの波打つ亜麻色の長髪は。 ここからでも分かる落ち着いた口もとは。 「枝理紗―――・・・!!?」 唯加のよく知る友、粉うことなき秋保枝理沙のものではないか。 ◆あとがき 第四話はいつもと比べるとちょっとシリアスの割合が大きかったような。 いや・・・唯加はラーディンと口論になってるし、いつも通りといえばいつも通り? またしても作者の趣味、ロマンスグレーと赤褐色が出ましたね。おっさんたち、好きなんです。 いよいよ次で最終話となりますが、そちらの方が『唯加らしさ』がよく出せそうです。 それでは今日はこの辺で。 JACKPOT59号掲載 題字フォント:S2G海フォント(STUDIO twoG) 背景画像:ひまわりの小部屋様 |