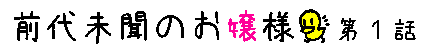 千里たつき 誰からもしっかり者と呼ばれる その時唯加はまだ幼稚園に上がるか上がらないかというほどの、ほんの小さな子どもだったのだが、周囲の大人は一つ上の長男と丁度生まれたばかりだった次女の世話に振り回され、唯加のことまでなかなか注意が向かなかったようだ。 実際、唯加はそんな小さな頃から落ち着いており、まさにしっかり者といえた。母親と引き離されても泣かないし、語彙も豊富で人見知りせず、初対面の大人とも話が出来た。 そんな少女がまさか勝手に家を出て迷子になろうとは、誰も思い至らなかったのだ。当然両親は動揺し、混乱して近所中を探し回った。ようやく裏山の麓の雑木林で見つかった時、唯加は目に涙をいっぱいに溜め、泣き出しそうなのを必死で堪えていた。 それから―――手にはぎゅっと大切そうに、金色のペンダントを握り締めていた。 朝八時を少し回った頃、唯加は図書室から借りてきた本を教室に持ち帰ってパラ読みしていた。 「唯加!」 名を呼ばれて顔を上げると、友人の姿があった。ハーフかと見紛うほど綺麗な亜麻色の髪と白い肌。 「おはよ、 「おはよう、相変わらず早いのね。また読書?」 枝理紗が整った微笑みを向けながら、前の机に鞄をかける。 その動作はいかにも落ち着いたお嬢さんという感じで、唯加はいつも感心してしまう。 「あれ、またって言われるほど読書してる?」 「してるわよー。絶対遅れないよう早くに登校するけど、皆なかなか来ないから暇なんでしょう?」 「あはは、まぁね」 唯加はそう答えて曖昧に笑った。彼女には何もかもお見通しのようだ。 毎日の習慣どおり、彼女らは他の友人も交えて予鈴が鳴るまで他愛のない話をしていたが、予鈴が鳴って皆がそれぞれの席に戻った後、二人だけが残ったとき思い出したように枝理紗が口を開いた。 「―――そうそう、唯加に頼みたいことがあったの」 「え、何?」 「そのペンダント、ちょっと見せてくれない?」 長い栗毛を弄んでいた指でそっと彼女が指し示したのは、唯加が幼い頃から大切にしている金色のペンダントだった。 「え、コレ? いいわよ」 制服の中に隠れていたペンダントを外し、唯加はそれを枝理紗の前に差し出す。 と、それを目にした一瞬だけ枝理紗の気配が揺らいだように感じた。 「やっぱり・・・・・・」 「枝理紗? どうかした?」 何事か呟く彼女の顔を覗き込むと、 「え・・・あ、ううん。あんまり綺麗だから見惚れちゃって」 そう言ってすぐ笑顔になった。いつものように余裕のある表情ではなかったが、唯加は特に気に留めなかった。 「気に入った?」 「うん、すごく綺麗ね。鷹の羽を模した形もいいけど、特にこの中央の赤い石が可愛い!」 「でしょー? 小さい時は分からなかったけど、今は結構気に入ってるんだ」 不意に枝理さの白く細い指が伸び、唯加の掌に載せられた金のペンダントを取る。 「昔、迷子になったときに拾ったのよね」 鑑定士のような目つきで、隅々まで調べるように眺めていく。興味津々のようだ。 「んー・・・それがよく覚えてなくて、いつの間にか握ってたの。間抜けでしょ」 そう言って唯加は苦笑したが、枝理紗はただきょとんとして首を傾けた。 「間抜け? 何言ってるのよ、唯加は誰よりもしっかり者じゃない」 整った微笑につられ、唯加も照れたように笑う。 「誰よりもって・・・そんなことないよー」 キーンコーンカンコーン・・・・・・ 本鈴が鳴った。はっとして黒板の上の掛け時計を見上げてから、唯加は不思議に思って呟く。 「先生、遅いわね」 言いながら見ると、枝理紗の人形のように整った顔から先ほどまでの笑みは消えていた。 「あのね唯加、・・・もう一つお願いがあるの」 「え、なに? 何でも言ってよ」 「うん・・・・・・」 頷くと枝理紗は、 「そのペンダント、一日だけ貸して欲しいの」 そう、困ったような表情で言った。 (あー、なんであっさり貸しちゃったのかなぁ) 授業中、未だかつて無いほど猛烈な後悔の念に苛まれつつ、唯加は心の中でぼやいた。 あのペンダントは幼い頃から肌身離さず大切にしてきた宝物だ。もちろん今まで誰にも貸したことなど無かったのに、あの後担任の教師が廊下を足早に歩いて来るのが見えたので慌てて了承してしまった。 (でもあんな困った 白のチョークで長い数式がずらっと書かれた黒板から、前の席に座る枝理紗の長く滑らかな髪へ視線を移す。 (いいわよって言ったらあんなに安心た顔が見れたから、まぁ・・・いっか) 苦笑いして、唯加は枝理紗の綺麗な笑顔を思い起こした。 「はい、では今日はここまで」 数学教師の良く通る声が聞こえ、唯加は慌てて立ち上がる。 「き、起立」 授業の初めと終わりの号令をかけるのは、クラス委員長である唯加の仕事だ。 「礼―」 自分の号令で次々に頭が下げられていくのは見ないことにしている。そもそも自分が誰より早く礼をするのだから、見えようもないが。 「委員長! 次のテストなんだけどさ・・・」 休み時間になった途端、唯加のもとには勉強を教わりに来るクラスメイトが必ずやって来る。次の時間は英語の小テストがあるので、出そうな文法を教えてくれとのことだった。 「―――だから、ここは分詞になるのよ」 一通り説明し終えると、彼らは口々に 「へぇ、さすが委員長。助かるよ!」 「阿隅さんって頼りになるよねー」 「もう、そんな事ないって」 褒められるのは得意ではないので苦笑するしかなかったが、誰かの力になれたというのは、素直に嬉しいことだった。 翌朝、着替えを済ませた唯加はペンダントをつけようとして、いつも仕舞っている位置にそれが無いことに気が付いた。 「あ・・・枝理紗に貸してたんだっけ」 何だか物寂しい。いつも持っていた宝物だからだろうか。 気を取り直して家を出ると、道の向こう側を歩く二人組の青年たちが見えた。 ぱっと見て違和感を覚えた。よく見ると一人は金髪、もう一人は青い髪をしている。 (・・・変わった色・・・・・・カツラ?) 唯加はそれだけを印象に残し、さっさと自転車を出して学校に向かった。 その日の午前中、枝理紗は学校に来なかった。珍しいが欠席なのだろうか。どちらにしろ枝理紗と会わない限り、ペンダントを返してもらうことは出来ない。 (やっぱりあれが無いと変な感じ・・・・・・) 無意識に胸元―――本来ならペンダントがあるはずの位置を手で押さえる。この心細くて寂しい感じは何なのだろう。お陰でせっかくの弁当も、ろくに手もつけないで片付けてしまった。 いつペンダントが戻るか分からない。枝理紗は欠席かも知れないし、遅刻かも知れない。そのことがひどく不安だった。 「唯加」 こちらに近付いてくる人影が見えた。聞き慣れた声でまさかと思い、顔を上げて確認する。 「―――枝理紗! 良かった、休みかと思っちゃったじゃない」 安心したのは枝理紗が来たからか、それともペンダントが返ってくるからか。 「ごめん、ちょっと用事が出来ちゃって・・・あとこれも」 枝理紗がさっと取り出したそれを見た途端、心の中がぐるんと回転したような気がした。心細さと寂しさできゅっとしぼんでしまっていた気持ちが、慣れ親しんだペンダントを目にするだけで一気に回復する。 「返すの遅れちゃったわね。ありがとう」 「ううん、いいよそんなの」 枝理紗の手からペンダントを受け取る。思わず唯加はそれを愛おしむように眺めた。 「―――良かった」 ただほっとして、自然に笑みがこぼれる。 「あ・・・ごめんね、大切なものなのに」 ペンダントがない間不安で仕方なかった唯加の気持ちに気付いたのか、枝理紗が慌てて頭を下げた。 「え、いいってそんなの。枝理紗は気にし―――あ、ごめん何?」 背後から掛けられていた声に気付いて、唯加はくるりと後ろを向く。そのせいで、申し訳なさそうにしていたはずの枝理紗がひっそりと笑んでいるのには気付かなかった。 「あのね唯加ちゃん、私いきなり委員会入っちゃって・・・すぐ行かなきゃならないんだけど、みんなのノート英語科の部屋にもって行ってくれないかな?」 お願い、と言って両手を合わせる友人の頼みを、唯加は二つ返事で承諾した。 「うん、いいよ。委員会頑張ってね」 昼休みの廊下を、唯加は足早に歩き出した。手には英語教師に提出するクラス全員分のノートを持ち、金色のペンダントもしっかりつけている。 後から枝理紗が慌てたようについて来た。 「唯加・・・大丈夫なの? 次の時間、音楽室まで移動じゃない」 音楽室は北校舎の五階にある。つまりこちら、南校舎の一階にある英語科の部屋からは、とてつもなく遠いのだ。 「大丈夫よ、今から急げば」 振り返り様に唯加は笑った。いつも頼まれ事をやり遂げんとしている時と同じ、生き生きとした笑顔だと枝理紗は思う。 (唯加らしいわね・・・・・・) 呆れている場合ではないが、そんな事を考えた。 「ていうかそれは枝理紗もでしょ? 先に行っててよ、音楽の先生ちょっと・・・かなり恐いし」 「え、でも・・・」 「枝理紗まで走らせる訳にいかないの。先行って、ね?」 立ち止まり、枝理紗の肩をとんと押してやる。 「うん・・・そうするわ。でも唯加、気を付けてね」 やたらと心配そうに言われ、唯加は何だか可笑しくなってしまった。 「どうしたの急に。別に何も起こらないって、このノート置いてくるだけなんだから」 笑いながらそう言って、唯加はまた歩き出した。 「・・・何も起こらなければいいけど」 残された枝理紗は音楽の教科書を胸に抱き、ぐっと唇を噛み締めてから逆方向へと歩き出した。 案の定、唯加は音楽室に向かって二階の渡り廊下を猛ダッシュすることになった。 「やっば、予鈴鳴ってる・・・」 午後の授業の始まりを知らせる本鈴が鳴るのは、今スピーカーから大音量で響いている予鈴の五分後だ。ギリギリ滑り込めるかどうか、かなり微妙なところである。 (あーもう何なのよ、ノート出すだけだったはずなのに色々話振っかけられるし) 話好きの英語教師は、しっかり者の相手を見つけて楽しいおしゃべりの時間を過ごせたが、唯加にとっては迷惑この上なかった。 (ったく、これじゃどんなに頑張ってもギリギリじゃないのっ) と、悪態を吐いたときだ。 南と北の校舎を繋ぐ渡り廊下の窓から、空にキラッと光る物体が見えたのは。 「―――え?」 その物体が光ったのは一瞬で、それ以降はひゅーっと音を立てて勢いよく・・・、 「こ、こっちに飛んでくる―――!?」 突然飛んできた謎の物体は加速してゆき、仰天して立ち止まった唯加の斜め前の窓を凄まじい音を立てて破壊した。 「え、え!? ちょ、何これあり得ない! だってこれ、これ・・・」 一瞬UFOかと思ったのだが、残念ながらそれほど希少価値の高そうなものではなかった。 「ひ、人・・・・・・ッ!?」 そう、窓を思い切り割って唯加の目の前に現れたのは、二人の青年だった。 着地した時の膝をついた姿勢から、むくりと最初に起き上がったのは二人のうち金髪のほうだった。背が高い。彼は唯加を見下ろすように一瞥してから、長い前髪をかがっとき上げた。 「おいティグリス、こんな餓鬼が新しい当主かよ?」 「―――餓鬼ですって!? ちょっとあなた、いきなり失礼だとか思んないの!?」 何故かいきなり我に返った唯加が食ってかかると、金髪の青年は面食らったように目を 「な・・・っ!?」 「口を慎めラーディン。お嬢様に失礼だぞ」 もう一人の青年が、フレームの細い眼鏡を抑えながらようやく立ち上がった。 「だってお前、こんな奴が―――」 「 眼鏡の奥の瞳から発せられる、鋭い眼光。 「・・・・・・ッ」 血の気の多そうな青年は、彼から目を逸らすようにこちらを見、そのまま黙り込んでしまった。唯加は一人状況が飲み込めず、ただぽかんとするしかない。 「えーと何、プルーフ・・・?」 眼鏡の青年が長い髪を揺らし、ようやくこちらを向いた。 「ご無礼をお許しください、お嬢様」 かと思えば、いきなりぺこりとお辞儀された。 「・・・え―――ちょっと、誰なんですかあなた方は? ていうかあの、とりあえず顔上げてくれないと困るって言うか・・・。あーもう、一体どうなってんのよ!?」 叫び出さずにはいられなかったヒステリー気味な唯加に、 「申し遅れました」 そう言って、ようやく顔を上げた眼鏡の青年は微笑みかけた。爽やかに。 「私はティグリスと申します。こちらはラーディン」 「ふん」 ラーディンと紹介された金髪の青年のほうはえらく不機嫌そうだが、放置しておいて良いのだろうか。 「いや、あの・・・名前じゃなくて」 「私どもは貴女の従者でございます。この度はお嬢様をお迎えに上がりました」 「従者? お嬢様ぁ? まさかそれって・・・私のこと?」 耳慣れない名詞が多すぎて、聞けば聞くほど混乱してしまう。そもそも唯加は枝理紗と違い、お嬢様などという存在とはかけ離れているのだが。 「ええ、貴女は我らがアストラル家の次期当主様にあらせられます。そのペンダントが何よりの 眼鏡の青年―――ティグリスと名乗った方だ―――が言いながら指したのは、唯加の胸元にかかったペンダントだった。 「これ・・・・・・?」 戸惑いながらも金色のペンダントをそっと握り締めた時、自分を呼ぶ声が聞こえた。 「唯加―――」 「あ・・・枝理紗!」 数メートル先にある北校舎の階段を、トントンと駆け下りてくる音が聞こえる。迎えに来てくれたようだ。 (あっ、そう言えば授業に遅れそうなんだっけ) ここにきてようやく思い出したので、唯加は怪しい青年たちを一瞥してから足を踏み出す。 「あの・・・私行かなきゃならないんで」 「チッ。もう来やがった」 せっかく背を向けたのに、ラーディンとかいう金髪の青年が舌打ちしたのが気になってまた振り返ってしまった。 「え、もうって―――」 「まずいな、まさかこんなに早く嗅ぎつけられるとは」 ティグリスという青年も顔を顰める。何があったというのだろう。 「来ちまったもんは仕方ねーだろ。めんどくせーからさっさと行こうぜ」 「そうしようか。では失礼致します、お嬢様」 「―――へ?」 何度目かの『お嬢様』を聞いた次の瞬間には、唯加の足は床から完全に離れていた。同時に視線もぐるりと天井へ向く。 「え・・・ちょっと、何するのよ!?」 唯加は、眼鏡の青年―――ティグリスによって、“お姫様抱っこ”されていた。 「おいお前、ギャーギャー喚くな。見付かるだろーが」 「やぁ―――!! 降ろしてえぇ―――ぇッ!!」 こんなに必死で形振り構わず叫んだのは、おそらく生まれて初めてのことだった。 「唯加、そこ? 何があったの!?」 首を伸ばしたり捻ったりして枝理紗の声がする方へ目を向けると、彼女は今まさに渡り廊下を走り出さんとしているところだった。 「枝理紗! どうにかして、こいつら―――」 シュン。 それは余りにあっという間の出来事で、ほとんど何も覚えていない。ただ、強い旋風が吹いたので反射的に目を瞑ったのは覚えている。 そして風が止み目を開けたとき、唯加はフカフカの椅子に座っていて、目の前には大勢の群衆がずらっと整列していた。 「・・・って、何これ!?」 咄嗟に立ち上がって見渡すと、斜め後ろから声をかけられた。 「お目覚めですか」 ティグリスの声だ。先ほどのことが衝撃的すぎて、もうしばらくは彼の名と声とを忘れることは出来ないだろう。 不意に立ちくらみに襲われた。それもそのはず、彼女は既に小一時間ほど気を失っていたのに目覚めて急に立ち上がったのだから。 「うぅ・・・何なのよ・・・」 言うまでも泣く気分を悪くした唯加は、頭を抑えながら高そうな椅子に座り込む。 そのとき彼女は、チカチカする視界の狭間に見てしまった。 号令もかけていないのに、次から次へと頭を下げていく人々を。 そして一斉に同じ言葉を発する。 「お待ちしておりました、お嬢様」 お帰りなさいませ、でなかったことは残念・・・否、この際関係ない。 ◆あとがき ぶっちゃけて言うと、この作品は完全に私の趣味と妄想の産物です。 具体的には委員長とかお嬢さんとか執事(違)とか、長髪メガネと金髪反抗期のコンビとか、もう全キャラが趣味。 あ、因みに長髪メガネ君ことティグリスの名前は近所のマンション『ティグリス枝川』から取りました。 決してトリ・ブラのパクりではございません。あ、でも好きですティグリス侯。 枝理紗さんは一応良家のお嬢さんっぽい名前にしたつもりです。枝の字がポインツ。 唯加とラーディンは・・・なんとなく(爆)。 それでは今日はこの辺で。 JACKPOT54号掲載 題字フォント:S2G海フォント(STUDIO twoG) 背景画像:ひまわりの小部屋様 |