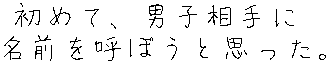 千里たつき
「うわ、気持ち悪い」 園田せりなが発したその言葉は、決して彼に向けられたものではなく、下手物好き、と言うより生き物全てを愛していそうな生物教師が生徒たちに回覧させた“ホルマリン漬けの食用ガエル”を目にしての、率直な感想だった。 短く太い円筒形をした容器は、白目を剥いた大きな蛙を、なんとか収容していた。満たされた液体はほぼ透明だが、腐敗したような色に見える。せりなはその中身の大きさと不気味さのあまり、一刻も早く後ろの席に回してしまいたかったのだが、それに触れるだけでなく持ち上げるなんて、見ているだけよりも余程おぞましいことに思えた。こんなものを「可愛らしい」などと言う生物教師も、せりなに言わせればどうかしている。 それが今あるのは、生物講義室特有の角が丸い長机の上で、生物の時間は、この長机一つに男女がひとりずつ座ることになっている。蛙入りの容器の位置は、幸いにも右寄りだったので、せりなは右隣に座る男子に、この蛙に関する一切を委ねることにした。 「ねえ…」 名前を呼ぼうとして、せりなはすぐやめた。その男子の顔も名前もわからなかった、という大きな理由はあるが、何より彼が、夢でも見ていそうなほど静かに、穏やかに寝息を立てていたからだ。 授業中に自分の腕を枕にして、こうもすやすやと眠れるものだろうか、と呆れながらも、せりなは蛙の白目と男子の寝顔とを見比べた。逡巡した結果、やはり隣の男子を起こすことにする。 「ねえ、ちょっと」 先ほどより少しボリュームを上げて、もう一度話しかけると、隣の席の男子の目がぐずぐず開き、同時に寝言とも返事ともつかぬ、曖昧な声が漏れた。せりなは呆れながらも、おぞましい円筒形のものを指して訊ねた。 「これ、後ろに回してくれる?」 「ああ、うん」 すぐに引き受けた彼は、大きな蛙に驚きもせず、しっかり両手で持ち上げた。その動作がごく自然だったので、この男子のことを何一つ知らないせりなは、男子だから平気なんだというふうに納得した。 しかし、彼が後ろの机の上にそれを置いた時、後ろからさっきせりなが言ったのと同じ言葉が聞こえた。 「うわ、気持ち悪い」 あからさまに嫌そうな、低い声。 あれが嫌な男子もいるのかと、せりなはまた驚いた。 「そうだ…ねえ、ありがとね」 せりなが思い出したように言ったお礼に、隣の男子はまた曖昧な声で返した。 後ろの席では、その更に後ろの男子も巻き込んで、蛙を気味悪がっている。 (男子だからじゃなくて、この人がすごかったんだ) 隣でまた居眠りを始めた男子を、せりなは少し見直した。 数日後、次の生物の授業中、ふと視線を感じて右を向くと、隣の男子と目が合った。 顔には見覚えがある。せりながそう思っただけだったのは、男子という生き物にほとんど関心がなかったからだ。実際ほんの数日前のことさえ、食用ガエルの不気味な白目のことしか憶えていなかった。 一方、生物講義室でだけ右隣に座るその男子は、どうしてかせりなの手元に目を移した。 「ねえ、私のプリント写してるの?」 返答は、またも曖昧な声。「うん」と言ったように聞こえた。 そうして彼は、せりなが教師の板書を写した、丁寧な文字を一通り書き写してしまうと、夢の世界へと旅立っていった。 (ひょっとしていつも寝てるのかしら) 静かに、穏やかに眠る様子を見て、せりなはふと思い出した。そうだ、前の時間も彼は寝ていた。それも相当ぐっすりと。 「ずっと寝てるから、板書写しそびれるんじゃない」 ちょうどせりなが呟いた時、生物教師が黒板消しを滑らせた。呆れて笑いがこみ上げた。 せりなにとって、在籍するクラスでフルネームと顔とが一致するのは、友達と何人かの女子だけ。一方ぱっと顔を見て「知ってる」と思える男子は、生物講義室でだけ隣に座る、ホルマリン漬けの食用ガエルを退けてくれた、いつも居眠りしてばかりだがプリントはとりあえず完成させる、少し強くて、少し可笑しい、あの男子だけだった。 ただしせりなは未だ、彼の名前を知らなかった。 「夏休み前に、席替えしようか」 ある日の生物の時間、生物教師が急にこう言い出し、ほとんどの生徒からは期待に満ちた歓声が上がった。けれどせりなは、嫌だと思った。なんとなくだが嫌だと思いながら、右隣を見た。男子が一人、長机に突っ伏して寝入っていた。 (私のことだから、顔と名前、席替えしたらずっと一致しないままだろうなあ) ぼんやり思考する自分に気付いたが、この男子には興味があるんだな、などと他人事のように感じた。 隣の男子とせりなの周りは、相変わらず騒然としている。 「席替え、楽しみだなあ」 「出席番号順なんて、もう飽きたもんね」 後方からそんな声が聞こえてきたので、右を見たまま考えた。番号順に並ぶと、自分のひとつ前になる男子の名前は何だったかを。 せりなでも、入学してから二度あったテストの答案が返却される時、何度も注意して聞いていた。ひとつ前の生徒が呼ばれる頃立ち上がって、答案を取りに行けば、ちょうど良いからだ。 しばらくそんなふうに思案して、席替えの日取りが報せられる頃ようやく思い出した。 せりなは言った。周りが騒がしいのをいいことに、夢の世界から、右隣の男子を呼び戻す程度のボリュームで。 「ねえ、『杉下』くん!」 すると彼は顔を上げて、目を白黒させながらはっきり返事した。 「はい! …あれ、園田さん?」 それを聞き、せりなは自分に呆れて笑った。 それと同時に、杉下をとても見直した。 生物講義室の隅の棚から、ホルマリン漬けの蛙が見ていた。 ■某文学賞に応募した作品です。結果? 訊かないで・・・! 今思うと、オチの一行は要らなかった気がします;(そりゃそうだ。 JACKPOT59号掲載 題字フォント:さなフォン(Heart To Me) 背景画像:Domenica様 |