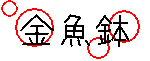 花笠柚癒
「晶君! 一緒に帰ろう!」 「おう。」 今日の終業式を機に一学期が終わって、明日から夏休みを迎える。 「翠、明日暇か?」 「うん? 暇だと思うよ。」 やっぱりはじめから遊ぶ気満々なんだ。もう宿題手伝ってあげるの止めようかな…自業自得ってことで。 「魚釣りに行こうと思うんだが、どうだろうか。」 「いいけど…この辺には川なんかないよ?」 「ここから自転車で三十分ぐらいのところにある。」 「まさか…そこまで行く気なの?」 「当たり前だろ。」 多分彼の言動からすると、ここから電車で三駅分先のところにある川のことだと思うんだけど、あの距離は明らかに三十分でいけるような生易しい距離じゃない。 「えっと…自転車で?」 「それ以外に方法があるとでも?」 「え、電車とか…あるよ?」 「電車は好かん。」 そ、そんな理由で…? 「で、行くのか?」 「え? あー…うん。行くよ。」 「んじゃ、決まりな。明日の朝七時に現地集合で。」 「え、私、道知らないよ…?」 「仕方がないな…じゃあ、お前の家までいってやる。」 「…ごめん。」 とりあえず、その日は晶君が妥協してくれた時間(午前八時半)まで、待ち合わせの時間を遅くしてから帰った。 きっかり八時半に晶君は、私の家のインターホンを鳴らした。普段は寝坊してやたらと学校に遅刻しているのに…。 「迎えに来た。早く出てこい。」 「あ、うん。今行く。」 前もって準備しておいた荷物を手に玄関へ早足で向かう。 「おはよう。晶君、しょっちゅう遅刻するのに今日は早いんだね。」 ちょっと皮肉のつもりで強調して言ってみる。 「時間がもったいない。」 「え、それってちょっと酷くない?」 「三十分で行くからな。」 あ…目が本気だ。どうしよう、私絶対に迷子になる…。晶君の体力、尋常じゃないもん…。 やっぱり、私はついていけなかった。原因としてはまず、自転車での移動は立ってペダルをこぐのが前提だったこと。それから、やたらと裏道を使って時間短縮をしたこと。私は初めてこの辺に来たから、裏道なんて何がどうなっているのかわからない。運良く晶君が見えるところに出られたみたいだったので、そこからさらに迷子になることはなかった。 「晶君…速すぎるよ…!」 「翠が遅いだけだ。」 「…どうせ、体力はないですよ。」 「ほら、ボーっとしてないで釣れ。」 釣竿を渡されたものの、正直釣りなんてしたことはない。 「やり方…わからないんだけど。」 「振って、糸をたらして浮きが沈んだら、リールをまけ。」 なんて簡素極まりない説明だろう。とりあえず、イメージでやってみることにした。 釣りを始めて一時間が過ぎようとしていた。私の竿にも晶君の竿にもいまだに一匹もかからない。 「つれないね…。」 「そんな日もある。」 「…てくれ。」 「…何か言ったか?」 「え、何も言ってないよ?」 「そこの人間たちよ…助けてくれまいか。」 「「…?」」 どこからか声がする。晶君が声のするほうに向かって走っていくから、私もついていった。草を掻き分けていくと、川から打ち上げられたのか、魚がぴちぴちと跳ねていた。人の姿はない。 「…誰もいない?」 「こっちだ、こっち!」 声のするほうを見ても、やはり魚が跳ねているだけである。どうしようもないので、ただその魚を注視していた。 「助けてくれ…いや、助けなくていい。あー、でもやっぱり助けてほしい。」 確かに魚の口が動いて、日本語をつむぎだしていた。晶君は、よほど今の目の前で起きていることが信じられなかったらしく頬をつねった。 「夢ではないぞ、少年。私は話ができる魚なのだ。」 「そんな魚がいるなんて、聞いたことないぞ。」 と、晶君は言う。彼は、魚釣りも好きだけど、魚についての知識も相当なものなのだ。よく教えてもらうのは、おいしい食べ方ばっかりなんだけど。 「当たり前だ。私は珍種中の珍種なのだからな!」 と、その奇妙な魚は得意げに言う。 「…って、しまった! 貴様ら、私が珍種の中の珍種だと知って、やつらのように売ろうと思ったんじゃないだろうな!?」 「思ってないですよ、そんなこと!」 「ところで、やつらって誰のことだ。」 「えー…とりあえず黒かったな。」 うっわ、なんてアバウトな…。 「そういや…さっきその辺で見たぞ。でかい水槽と網持ってた。」 「ギャー、つかまる! 売られる! 殺される!」 「うるさいな、お前。そんな大きな声で騒いでたら見つかるぞ。」 「でも、もし本当にそんな目にあうんだったら…この魚、私たちがつれて帰ろうか。」 「…そうだな。」 私が彼(?)を晶君が持ってきていたクーラーボックスの中に詰めようとしたが、彼は飛び跳ねながら逃げていく。が、それもつかの間、あっさりと晶君に捕まえられた。 「んな、追いつかれないと思っていたのに!」 彼は本気で逃げ切れると思っていたらしく、真剣に驚いていた。それでも必死に抵抗を続ける彼をクーラーボックスに入れるのは大変なことで、とりあえず、魚は持ち主である晶君の家に引き取られることになった。 「すまん、俺にはできない。」 次の日の朝早くに、クーラーボックスをもって、晶君が家にやってきた。どうやら、晶君とあの魚は徹底的に気が合わないらしく、私に預けに来たらしい。 「でも…魚を入れる容器が…あ、そうだ。」 私は物置代わりになっている部屋に向けて走る。そこから、一昔前まで使っていた金魚鉢を掘り返し、水を入れた上で玄関へ戻る。 「これになら入るかな?」 「…少し小さいかもしれないが、とりあえず入れてみるか。」 クーラーボックスが開けられる。中では、ぴちぴちと魚が暴れている。しかし、光を浴びておとなしくなった。 「おぉ、天から光が入ってきたぞ!」 その台詞から察すると、どうやら昨晩から光を浴びていなかったらしい 「魚、お前の新しい家が決まった。」 「またこんな暗いところなんじゃないだろうな。やっぱり貴様ら、私を売る気…」 「透明で外が見えるぞ。光も入り放題だ。」 「いいだろう。引っ越す。」 長い間、暗いところにいたせいもあるのだろう、いとも簡単に魚の意志は折れた。 「じゃあ、入れますね。」 そういって、魚を金魚鉢に移す。と、狭さのせいで有無を言わさず魚は身動きを取れなくなってしまった。 「ちょ、狭い! 光は入り放題で、外は見えるしで最高だけど狭い! ダメではないか、人間もっとゆとりを持たなくては!」 「お前、魚だろ。」 「でも…ちょっとかわいそうだったかな。」 だが、これ以外に入れ物はないため、あきらめてもらうほかない。 「とりあえず、名前を決めてあげようか。」 「いらん! 名前などあったところで何にもならないだろう!」 「じゃあ、『お前』とか『そこの魚』とかでいいのか。」 「それは許さん!」 「じゃあ…『内藤さん』でどうですか?」 「…何故に『内藤さん』?」 「えっと…親戚の人の名前を借りたんだけど…。」 「私はお前の親戚ではない!」 「私は『お前』じゃなくて『水樹(みなき)』ですよ。」 「俺、『市(いち)来(き)』。」 今更な上に簡素極まりない自己紹介を終えると、しばらく内藤さんが考え込む。そして、言った。 「内藤は百歩譲って許してやろう…だが、『内藤さん』ではなく『内藤様』と呼べ!」 「お前にそんな威厳はまったく見受けられない。」 「ダメですよ、内藤さん。『内藤さん』で一つの名前なんですから。」 「え、嘘!? それは反則じゃないのか!」 「嘘じゃないですよ。晶君、内藤さんは私が預かっておくよ。たまには、晶君も会いにきてあげてね。」 「誰が好き好んでこんな魚に会いに来るか。」 「ふん、私だって貴様のようなやつの顔など見たくもないわ。」 恒例になってきた口げんかをひとしきり終えた後、晶君は帰った。 時の流れは早いもので、夏休みも後一週間を残すのみとなった。そんなある日、また晶君があの日のように釣りセットを持ってやってきた。 「川へ行こう。」 「また釣り?」 「それもある。もう一つは、内藤がどういう成り行きでやつらに追われて、あの川まで逃げてきたのかを思い出させるためだ。」 しかし、今度はいきなりのお誘いだ。行くも何も、まずは準備をしないといけない。 「内藤は?」 「うん? あぁ、私の部屋にいるよ。」 晶君が一瞬、眉をひそめた気もするが、気のせいだろう。 「とりあえず、俺は先に行ってるから、準備ができ次第きてくれ。」 「わかった。…やっぱり今度も自転車なの?」 「もちろん。」 それを聞いてため息をついた後、私は部屋に戻って準備を始めた。内藤さんには悪いが、自転車のかごに入れるために金魚鉢ごと袋に入ってもらう。それから私は、川へ向かった。 (…釣れない。) 早いうちに来たのはいいものの、以前と同じようにまったく魚は釣れなかった。それに何より… 「遅い。」 目的の人物を探すように辺りを見回す。 「…まだ探してんのか、あいつら。」 内藤が言っていた、黒い人々があたりをうろついている。 「おい、そこの少年。」 そして、その黒い人々から声をかけられた。 「この辺でしゃべる魚を見なかったか。」 「おっさんたち…頭、大丈夫か。しゃべる魚なんているわけねえだろ。」 「ふん、その様子だと知らないようだな。」 たとえ、知ってたとしてもいわねえよ、と内心で思いながら、知らないと念を押そうとしたときだった。 「あ、晶君! やっと見つけたー。」 しまった。おそらく彼女の自転車のかごの中には───! この前も一度来たはずなのに、散々迷い続けてようやく川が、晶君が見えたとき、私はうれしくなって彼を呼んだ。晶君は私のほうに振り向き、何で来たんだ、といった風な視線を送ってきた。来いといったのは晶君なのに、と思いながら、その場に自転車を止める。が、よく見ると、晶君の周りには内藤さんが言っていた黒い人々がいたのだ。声が小さかったから、何を言っているのかはわからなかったけど、黒い人々がいっせいに私のほうに向いた。背筋に寒気が走る。 「おい、翠、なにしてんだ! 早く内藤つれて逃げろ!」 彼の叫び声を受けて、私は反射的に自転車のかごにある袋に手を伸ばし、走った。しかし、大の大人に勝てるわけもなく、あっという間に追いつかれてしまう。 「お嬢さん、おとなしくその袋の中身を渡してはもらえないだろうか。」 リーダー格であろう男が、顔に柔らかな、それでいて決してやさしさを含まない笑顔を貼り付けながら言った。 「誰が、お前たちなんかに…!」 「どうした、水樹。何かあったのか?」 「ほう、やはり中にはあのしゃべる魚がいるのだな! そうとわかれば、余計に引くわけには行かない。お嬢さん、その魚を…」 「内藤さんは、渡さない!」 チッとその黒い人は舌打ちをし、また元の笑顔に戻って私に言う。 「では、お嬢さん。この魚の売り上げの半分を差し上げましょう。それでいかがです?」 「売り上げなんてどうでもいいですよ!」 とはいったものの、そろそろ苛立ちが相手の顔に色濃く出てきている。 「水樹、私をやつに渡せ。」 「え、内藤さん…?」 「やつらの目的は私だ。」 「ほう、お前自ら売られようというのか。殊勝な心がけだな!」 「ダメです、内藤さん!」 「水樹。いいから早く、この袋をやつに渡せ。」 こうなったらもう、何を言っても聞かないんだろうな…。悔しいけど、黒い人に袋を渡そうとした。が、その黒い人が急にふらつき倒れこむ。 「何、格好つけようとしてるんだよ、内藤の癖に。」 その後ろから現れたのは、どこで拾ったのか木の棒を携えた晶君。どうやら、それで黒い人を殴ったらしい。さすが剣道部…というかこの人…後でちゃんと起きるよね? 「俺はこいつら全員殴り倒すから、お前はその間に警察にでも通報しとけ。」 「あ、うん!」 ポケットから携帯を取り出す。 「水樹。電話をかせ、いろんな罪をこいつらに擦り付けてやる。」 「いいですけど…あらぬ罪は擦り付けちゃダメですよ?」 通報を受けた警察がやってきて、黒い人々は連行されていった。ただし、晶君のせいで意識はあらぬところへいったままで。 それから、残りの夏休み、私は遊びに行くところがどこであろうと、内藤さんの希望により金魚鉢を持って移動した。内藤さんは、彼の希望により今も私の部屋に住み着いている。そして新学期が始まった。 「どうした、『金魚鉢少女』。」 新学期、顔をあわせて早々こういわれた。 「あ、晶君まで! 止めてよ、そのあだ名。あんまり好きじゃないんだから…。」 「どこへ行くにも金魚鉢と一緒だから金魚鉢少女。いいじゃないか、ぴったりで。」 と、晶君は意地悪く笑う。こんなことになったのも、言っちゃ悪いが、内藤さんのせいだ。このときだけはちょっと内藤さんを拾ったのを後悔せざるを得なかった。 =恐れ多くもあとがきを書いてみる= こんにちは、花笠です。相変わらずのヤマなしオチなし状態です(あえて最後のひとつは言うまい)。そして、染井さん。本当に締め切りぶっちぎってごめんなさい。四コマのプロットもグダグダでごめんなさい! 私にギャグの才能がないのはわかっていたことなんですが…。部長さん、学園モノというジャンルを華麗にスルーしまって申し訳ないです。(待 本編にはまったく関係のないどうでもいい設定ですが、市来君は水樹さんに片思い中です。だから、自然と水樹さんの部屋に居座っている内藤さんがうらやましくて、憎たらしくて仕方がないのですね。あ、でも口数が少ないのは照れからではなく、もともとです。 ではでは、またどこかでお会いしましょう。花笠でした。 2008年度文化祭特別号『ff』α掲載 題字フォント:あずきフォント様 背景画像:空に咲く花様 |